2025年9月、社内向けのPower Automateの講座を開催することになりました。
参加予定者は600人。(9/6現在)
ITとは無縁だった自分が、たった半年のPowerAutoamteの学びを経てこんな場を持てるようになるなんて、正直びっくりしています。
そして今ちょっとびびってます。
でも、これは決して自分ひとりの力ではありません。
(なにせプログラミングセンスが皆無です)
きっかけは2025年1月にPower Automateの学習を始めたとき、同時に出会ったMicrosoft Copilotでした。
この存在が、学びを続けるうえで本当に大きな支えになりました。

Copilotなしでは一人でPowerAutomateの学習を続けてこられなかったと思います
PAD推進から見えた現実
実はその前から、Power Automate Desktop(PAD)の社内講座を2023年から2年間ほど推進してきました。
業務効率化のために何かできればと思って始めた活動でしたが、
とにかくぜんぜん使ってもらえない。
とにかくぜんぜん浸透しない。
とにかくぜんぜん興味をもってもらえない。
理由はシンプルで、みんな本業が忙しくて、新しいツールを学ぶ時間が取れないんです。
自分はPower Platform専任なる前は同じ状況でしたので、その人たちの気持ちもよく分かります。
「効率化したいけど、学ぶ余裕がない」――そんな声を何度も聞きました。
クラウド版への挑戦とCopilotの支え
それでも、Power Platformの可能性は信じていました。
社内になんとなく漂う
「何をやっても無駄」
「これまで通りが一番。新しいことは始めたくない」
(※あくまで個人的な感想です)
こんな空気(閉塞感?)を変えられるのは、
仕事のやり方を根本から変えられるPowerPlatformだと思っていました。

業務を変える力があるこのツールを、もっと多くの人に届けたい。
そう思って、2025年1月からクラウド版Power Automateの学習をスタート。
そこから活動の幅を広げていきました。
そのタイミングで出会ったのがCopilotです。
PADを独学で学んでいた頃は、書籍やブログ、YouTubeを頼りに何とかフローを作っていましたが、
条件分岐?繰り返し処理??という状態。
エラーが出るたびに「もう無理…」と心が折れていました。
でもCopilotがいてくれることで、「エラーが出ても、なんとかなるかも」と思えるようになってきており、それが、学びを続けられる大きな転機でした。

この半年間。始業時から終業時まで、ずっとCopilotとやり取りして学習。
会話数(やり取り)は一万を軽く超えていると思います。
※こんなにPowerPlatformに集中できる環境で仕事をさせてくれている会社には本当に感謝です。
講座設計のこだわり:「使う」をゴールに
半年間のPowerAutomate学習期間を経て、自分が学んだPowerAutoamteに関することを多くの人に共有したいと思うようになりました。

単純に 自分の中にだけ留めておくのはもったいないなぁ と思うようになりました。
そして2025年9月にPowerAutoamte講座を社内向けにスタートすることにしました。
多くの講座が「フローを作れるようになる」ことを目指しますが、私はそれをやめました。
代わりに、「知る・使う・作る」の3ステップを定義して、
最終目標をフローを「使う」に設定しました。
こちらが用意したサンプルフローを、ただ使ってもらうだけ。それでも業務改善は十分に可能です。
まずは「使う」ことで、自分の業務が自動化されて楽になる――そんな実体験を得てもらいたい。それが、次のステップへのきっかけになると思っています。
600人の参加と情報発信への葛藤
今回600人もの参加者が集まったことには、本当に驚きました。
そして同時に、多くの人にとってフローを「作る」ことは非常にハードルが高いことである。
ということを改めて再確認することができました。
でもフローを「作る」には不安がある。時間がかかる。
だからこそ、ハードルを下げる講座が必要なんだと実感しました。
社内・社外への情報発信については、正直ちょっと葛藤もあります。
「こんなことができるよ」と発信すると、称賛を求めているように見られるんじゃないか…と不安になることも。
でも、自分が知ったことを自分の中にとどめておくのは、やっぱりもったいない。
誰かの役に立つかもしれない――そんな気持ちを大切に、これからも発信を続けていきたいと思っています。
おわりに
Power Automateは、非IT人材でも業務改善の力を手にできるツールです。
そして、Copilotの存在があったからこそ、ここまでPowerPlatformの推進活動をここまで続けてこられました。
これからも、等身大の姿勢で、誰かの「やってみよう」のきっかけになれるような活動を続けていきます。
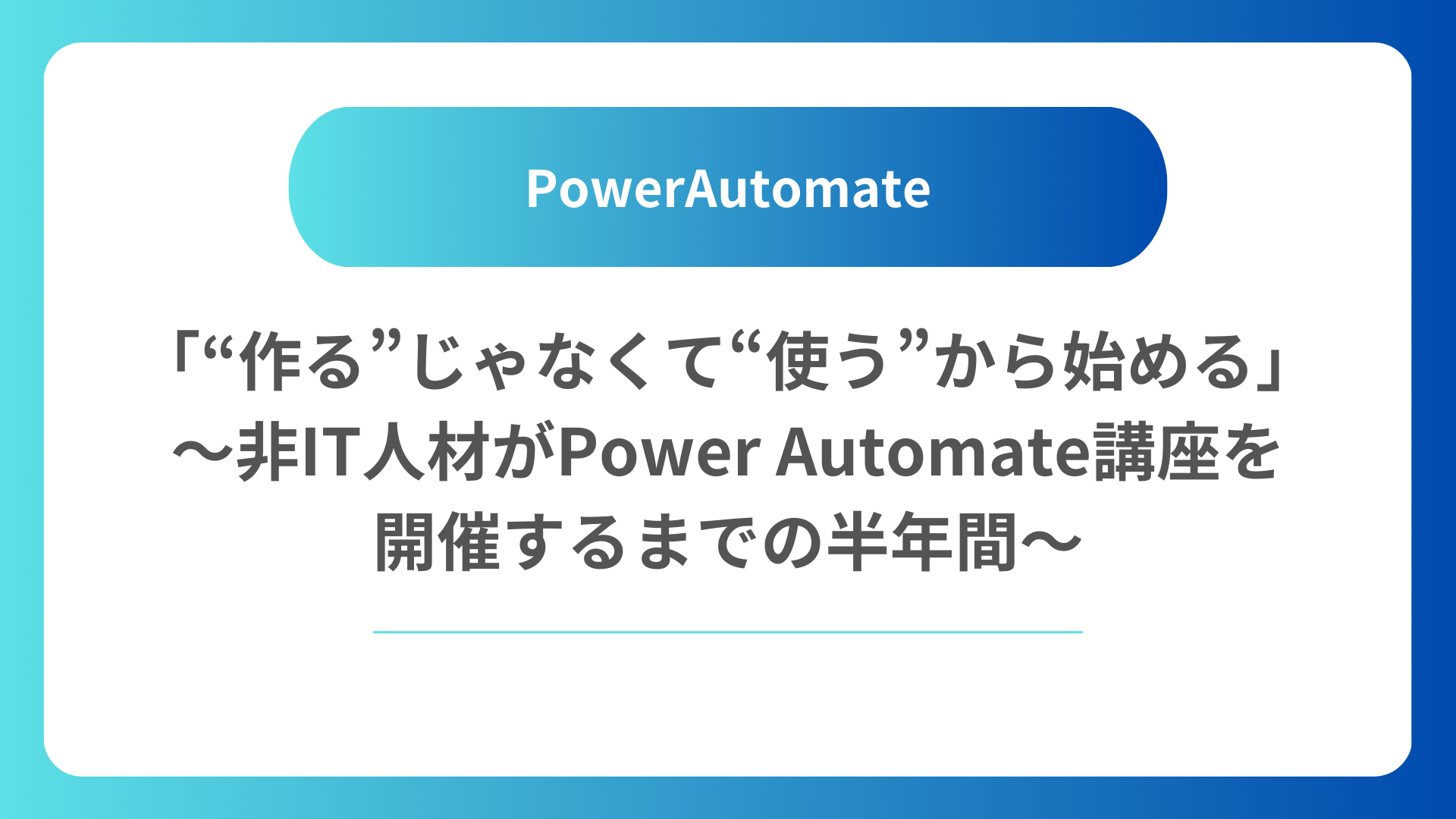
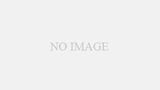
コメント